自然の風景を絵に描こうと思ったとき、一番よく使う色のひとつが「緑いろ」です。
草や木、山や森など、自然の中にはたくさんの緑が見られます。
けれど、絵の具セットに入っている緑だけでは、すべての自然の色をうまく表現できないこともあります。
たとえば、葉っぱの表面をよく見ると、光が当たっているところは明るく、影の部分は暗く見えます。
そこに水滴がついていたり、小さな虫に食べられたあとがあったりすると、さらに多くの緑が必要になります。
でも安心してください。そういった細かい表現も、基本の色を組み合わせれば、かんたんに作り出すことができるんです。
この記事では、絵の具でいろいろな緑色を作るためのコツやアイデアをごしょうかいします。
自然の緑をよりリアルに表現したい人は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
緑の絵の具が手元にないときの対処法
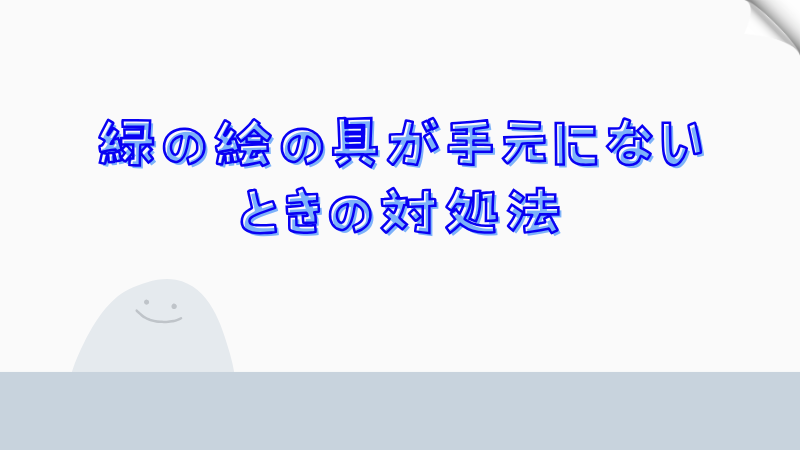
もし、絵の具の中に緑色が入っていなかったとしても、大丈夫です。
青と黄色、このふたつの色を混ぜるだけで、きれいな緑色を作ることができます。
青も黄色も、ほとんどの絵の具セットに入っている基本の色なので、手元にあることが多いと思います。
混ぜるときは、黄色の絵の具を先に出して、そこに青をすこしずつ足していくのがおすすめです。
青の絵の具は、色がとても強いので、一度にたくさん入れてしまうと、思った色よりも暗くなってしまうことがあります。
それに、前に使った色が筆に残っていると、色がにごってしまうこともあります。
だから、絵の具を混ぜる前には、筆を水できれいに洗っておくことも大切なんです。
様々な緑色を作り出すための色の調合テクニック
緑という色は、一色だけではなく、明るいものから暗いものまで、いろいろな種類があります。
そのため、ただ青と黄色を混ぜるだけでなく、そこに別の色を加えることで、自分だけの特別な緑色を作ることができます。
また、すでに混ぜた緑色に少しだけ違う色を足すことで、同じような色を何度でも再現しやすくなります。
これは、絵をくり返し描くときにとても便利な方法です。
まずは、基本の緑色をうまく作ることからはじめて、そこから応用していくと良いでしょう。
いくつかのテクニックをご紹介するので、自分の作品に合った方法を探してみてくださいね。
黄緑を作るコツ
明るく元気な印象の黄緑色を作るときは、緑色に黄色をすこしずつ加えていきます。
黄色の量がふえるほど、色が明るくなり、目立つ感じになります。
黄緑を作るときの目安は、緑と黄色を1対1で混ぜることです。
このくらいのバランスにすると、アマガエルのようなはっきりした黄緑色が作れます。
春の草や新芽など、あかるい自然の風景にぴったりの色です。
深みのある深緑の作り方
暗くて落ちついた雰囲気の緑を作りたいときは、緑色に青をすこし多めに加えてください。
それにくわえて、ほんの少しだけ紫色を混ぜると、深みのある色合いになります。
紫には赤色の成分がふくまれているので、ただ青と緑だけを混ぜるよりも、色に奥行きが出ておもしろくなります。
この深緑色は、森の中や、木の影など、暗くて静かな場面を描くときにぴったりです。
混ぜるときの目安は、緑2:青2:紫1のバランスです。
青緑の調整方法
青緑色を作るときは、緑色に青をすこしずつ加えていく方法がいちばんやさしいです。
青と緑を同じくらいの量で混ぜると、信号機で見るような青緑に近い色ができます。
この色は、水のある場所やガラスのような表現にもよく使われます。
表:緑色のバリエーションとその作り方
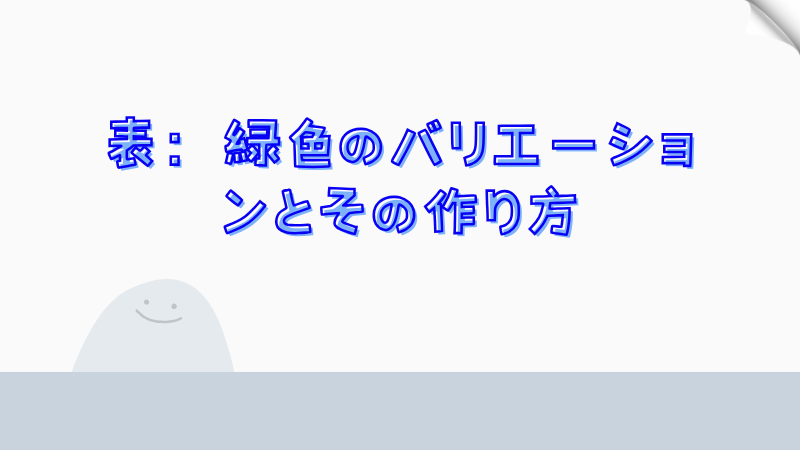
| 緑の種類 | 基本の配合 | 特ちょう・使い道 |
|---|---|---|
| 黄緑 | 緑 + 黄色(1:1) | 明るくて目立つ。春の草や若葉に向いている。 |
| 深緑 | 緑 + 青 + 紫(2:2:1) | 落ち着いた色合い。森や影のある場所に使える。 |
| 青緑 | 緑 + 青(1:1) | すずしげで透明感がある。水辺の表現にぴったり。 |
日本の信号機と「青」のふしぎな関係
日本の信号機では、「進め」を意味する色を「青」と言いますが、よく見ると少し緑がかった青に見えることがあります。
これは、日本語で「青」と「緑」の区別が昔はあいまいだったためです。
たとえば、「青りんご」「青いみかん」「青葉」など、本当は緑に近いものも「青」と呼ばれています。
とくにお年寄りの方は、緑の葉っぱのことを「青葉」と言うなど、今でも昔の呼び方を使う人が多いです。
このように、日本の色の名前には文化や歴史が深く関わっていることがわかります。
自然な風景を描くための緑色の調整法
市販されている絵の具の緑色は、カラフルでとてもきれいです。
ですが、自然の風景を描くときには、そのままだと少し派手すぎることがあります。
そこで、自然らしく見えるように色をおさえるテクニックが必要になります。
一つの方法は、白や黒の絵の具を少しだけ混ぜて、明るさや暗さを調整することです。
また、赤や茶色、紫などの色をほんの少し足すと、緑にちょっとしたニュアンスが出て、リアルに見せることができます。
たとえば、茶色を少し加えると、秋の森のような落ち着いた緑になります。
それから、いくつかの色を重ねてぬったり、水でうすめてぼかしたりすることで、自然に近い表現ができるようになります。
葉っぱの表面や影の部分、日光が当たる場所など、それぞれにちがう緑を使い分けることが大切です。
まとめ:緑色は工夫次第で無限に広がる
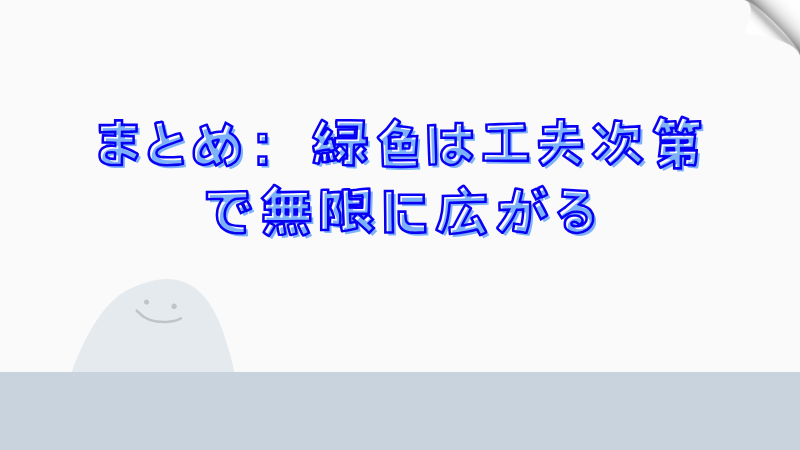
きれいであざやかな緑色の絵の具は、ポスターやかざりに使うと、とても目立って楽しいです。
でも、自然の風景をえがくときには、そういった強い色をすこしやわらげる必要があります。
緑色を自然らしくするには、色をくすませるテクニックがとても大切です。
そのためには、白や黒を少し混ぜたり、赤みのある色を足したりするなど、いろいろな方法を試してみるのが良いでしょう。
そして、自分の目で自然をよく見て、その色をまねしてみることもとても大切です。
たとえば、公園で子どもたちといっしょに葉っぱを見ながら、「この葉はどんな色かな?」と話すのもいいですね。
「黄色っぽい?それとも青っぽい?」と考えながら色をくらべることで、色を見る力が自然と身につきます。
自然の中には、言葉では言いあらわせないほどたくさんの緑があるのです。


